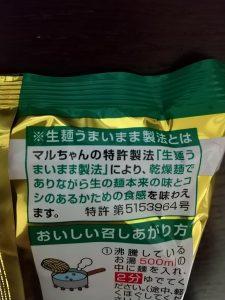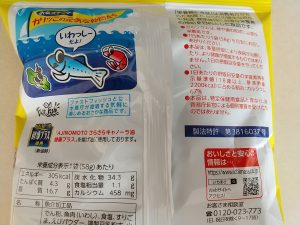ロケ先で訪問した人の仕事や生活等を紹介するテレビ番組で、過去に取材した人の数年後を追って再訪問する企画があります。その手法に倣って今回は、6年前(2015年12月16日)のブログで紹介した「多色ペンライト」の特許(第5608827号公報、2014年9月5日登録)がその後どうなったかについてお知らせします。

















この特許は、登録から5年後の2019年3月19日に進歩性を理由として無効審判を請求されました。特許権者(ターンオン社)は請求項1、2を訂正しましたが、特許庁は、「本件発明は、甲1発明、甲2に記載された技術事項及び周知技術に基づいて、当業者が容易に想到することができた」として、2020年7月28日に無効審決をしました。それに対し特許権者は、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を起こしました。
2021年10月6日、知的財産高等裁判所は、「特許庁がした審決には甲1発明の課題の認定の誤りがある」と判断し、審決を取り消す判決をしました。この判決が確定したため、特許庁は、2022年1月13日、本件特許は無効でないとの審決をしました。
このように紆余曲折を経て、本件特許は存続しています。なお、この特許の対象製品である「多色ペンライト」は、ターンオン社のホームページにも掲載されています。(コナン)
https://turnon.co.jp/patent/